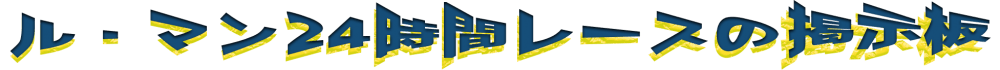常識を覆したレイアウトへの果敢な挑戦
2015年、日産がル・マン24時間レースに投入したプロトタイプマシン「GT-R LM NISMO」は、耐久レースの常識を根底から覆す構造で世界を驚かせました。最大の特徴は、通常では考えられない前輪駆動(FF)レイアウトで設計されていたことです。これまでル・マンに登場したLMP1マシンのほぼすべてが後輪駆動または4WDだったなかで、この挑戦は極めて異例のものだったのです。
GT-R LM NISMOは、FWDに加えてフロントにエンジンとギアボックスを配置し、重量配分も前寄りという構成を採っていました。これは、長時間にわたるレース中のタイヤ摩耗の均一化や空力効率の最大化を狙った、非常に理詰めの設計方針によるものでした。さらに、車体全体をできる限り低く抑え、フロント部分を大きく使ってダウンフォースを生み出す構造もユニークでした。
常識を打ち破る設計に対する注目度は高く、多くのモータースポーツ関係者やファンから「日産がル・マンに革命を起こすかもしれない」と期待されていたのです。
理論と現実の狭間で直面した数々の課題
理論上は筋の通った革新設計だったGT-R LM NISMOですが、実戦投入においては数々の課題が露呈しました。もっとも顕著だったのは、トラクション性能の不足です。前輪駆動では、加速時に荷重が後ろへ移動するため、駆動輪であるフロントタイヤが空転しやすく、加速効率が下がってしまいます。これにより、他のLMP1マシンと比べて立ち上がり加速で明確な差が出てしまったのです。
また、日産は当初このマシンにエネルギー回生システム(ERS)を搭載する予定でしたが、開発が難航し、2015年のル・マンではERSを搭載しない状態での出場となりました。このことが、トップカテゴリーにおいて致命的なパフォーマンス差につながり、予選・決勝ともに苦戦を強いられる結果となりました。
さらに、複雑な空力設計とFF構造によって、ドライバーへの負担も大きく、安定性やコントロール性において他チームとの差が浮き彫りとなっていきます。レースにおいては、3台体制で参戦したものの、完走を果たしたのは1台のみ。しかも、トップから10周以上離された結果となりました。
失敗ではなく「次」に繋がる革新の証
GT-R LM NISMOの挑戦は、結果だけを見れば「失敗」と捉えられるかもしれません。しかし、その背景にある思想や設計哲学は、今もなお多くのエンジニアやファンの間で評価され続けています。
日産はこのプロジェクトを通じて、レギュレーションのなかで最大限の独自性を発揮し、「最速であるためには必ずしも常道を行く必要はない」という姿勢を貫きました。たとえ1回の挑戦で表彰台を掴めなくとも、そこに注がれた設計思想や知見は、後の市販車開発やレース車両設計に活かされていきます。
たとえば、FFでありながら高いトラクション性能を発揮するためのサスペンション技術や、空力ボディのノウハウは、日産の技術資産として蓄積され、他モデルへの展開も期待されています。加えて、他メーカーが保守的になる中であえて新しい構造に挑んだ姿勢は、モータースポーツが本来持っていた“実験と進化の場”という意義を再認識させるものでした。
GT-R LM NISMOは表彰台に立たずして、その存在意義を確かなものにしたマシンといえるでしょう。型破りであることを恐れず、未来に種をまいたこの異端のGT-Rは、いつか再び、別のかたちでル・マンに帰ってくるのかもしれません。