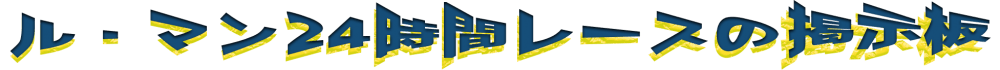自然吸気からの脱却とル・マン制覇への野望
1970年代後半、ル・マン24時間レースにおいてエンジンの性能競争は新たな段階に入りつつありました。従来の自然吸気エンジンによるパワー向上には限界が見え始め、より高効率な出力を求める動きが顕著となっていたのです。
そうした流れのなか、いち早くターボチャージャーの導入に踏み切ったのがフランスの自動車メーカー、ルノーでした。ルノーは1975年にル・マンへの本格参戦を開始し、試験的にターボエンジンを搭載したプロトタイプを開発。その集大成として投入されたのが、1978年型「ルノーA442B」でした。
このマシンは、ターボ過給機を装備した直列4気筒2.0Lエンジンを搭載し、最高出力は約500馬力。当時としては破格の数値であり、しかも空力に優れたロングテールボディとの組み合わせによって、ル・マンで重要とされる高速域での安定性も備えていました。
A442Bのターボ性能がもたらした圧倒的優位性
A442Bの最大の特長は、やはりそのターボエンジンによる加速性能でした。ストレートでは他車を圧倒するスピードを見せ、特にミュルサンヌ・ストレートではその強さが際立っていました。従来の自然吸気エンジンでは届かないパワー帯域を持ち、高速巡航時にも余力を残した走りが可能だったのです。
ただし、当初は信頼性に課題もありました。ターボは高回転・高温領域での運用が基本となるため、エンジンへの負担は大きく、耐久レースではリスクを伴いました。事実、1977年にはA442が有力なポジションを走っていたにも関わらず、エンジントラブルによって完走を逃しています。
しかし翌1978年、改良を重ねたA442Bはついにそのポテンシャルを完全開花させます。ドライバーはジャン=ピエール・ジャブイーユとディディエ・ピローニ。過酷な24時間を通して大きなトラブルもなく走りきり、見事に総合優勝を果たしました。これはフランス車による初のル・マン制覇としても記録されています。
ターボ元年が築いた耐久レースの新基準
A442Bの勝利は単なる1メーカーの快挙にとどまりませんでした。ル・マンという舞台において、ターボエンジンの有効性を世界に示した歴史的な瞬間だったのです。以後、グループCカテゴリーやF1でもターボ技術が急速に普及し、1980年代には“ターボ時代”と呼ばれる潮流が形成されていきます。
この勝利を最後に、ルノーは耐久レースからの撤退を選び、F1活動へとシフトしますが、A442Bが残したインパクトは後続のマシンたちに明確な影響を与えました。実際、ポルシェやBMWといったライバルメーカーは、その後次々とターボエンジンを搭載した耐久マシンを開発し、技術革新の加速を後押しすることになります。
現代においても、ル・マンに出場するハイパーカーやLMDhマシンはハイブリッドや過給技術を前提とした設計が基本となっており、A442Bが切り拓いた「効率と出力の両立」という思想は脈々と受け継がれているのです。ルノーのターボ革命は、耐久レースの進化にとって必要不可欠な一歩だったといえるでしょう。